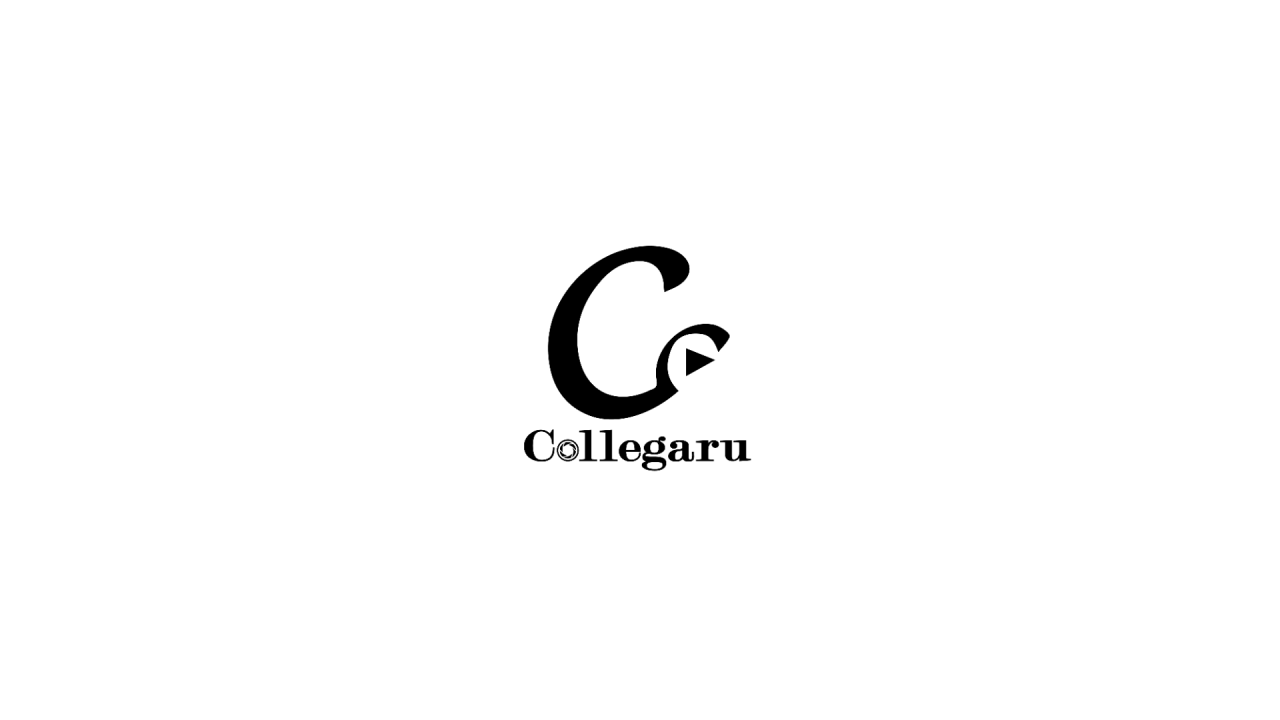最近のウェディング業界の映像制作で思うこと
2024/05/27
皆さん、こんにちは。
普段、あまり個人的な意見・感想を述べることは当サイトでは行ってきませんでしたが、どうしても発信したい思いがあり、今回特別に、コラムページを活用し思いを綴ることにしました。
テーマは『最近のウェディング業界の映像制作で思うこと』です。
かなり長文で硬い文面ですが、お時間のある方は是非最後までご覧いただけますと幸いです。
目次
インスタで流行、個人クリエイターによるシネマ調のエンドロール
近年、個人事業主を中心としたエンドロールのクオリティが上がってきている。
独特の空気感はカッコよさ、クールさという言葉がマッチし、制限の多い、所謂、会社請けでの映像制作では難しい表現がなされていることが多い。インスタグラムなどを介して、クリエイターの持つ個性全開の映像を好むお客様も徐々に増え、一種の流行が波及してきている現状である。
そうした“流行り”を受けて、ウェディングを専業とする映像会社もこぞってこうした流行りに乗ろうとしている。それ自体は素晴らしいことで、トレンドにレーダーを張れることは誇れることと思う。
だが、ここで少しおかしな傾向が見て取れるようになった。
それは、あくまで“流行り”であるものを“スタンダード”として捉える企業が増えたことだ。
個人的にあまり好きな表現ではないが、俗称『シネマエンドロール』なるものとして、
一部の企業で扱われるようになってきている。
流行りの映像を主張する企業がお節介の域を超える
ここでなぜ「おかしな傾向」と揶揄するかというと、そもそも結婚式というものに於いて最優先なのは「新郎新婦の意思を尊重すること」にある。「やりたい」をできるだけ叶え、状況に応じ最良の回答を用意することが、ウェディング業界に属する者としての仕事である。大袈裟な言い方をすれば使命とも言える。
ところが、近年の流行りをスタンダードとする企業は、「自社のやりたいこと」を新郎新婦に強要する傾向がある。強要と表現するとすこし言葉が強くなるが、要は「当社では流行りの映像に沿って、感動的なエンドロールを制作いたします」といった売り文句を提示するわけだ。
ここで流行りの映像の一部について触れていきたい。
通常のアーティスト楽曲を使用せず、シネマティックな著作権フリー音源を採用した独特のテイストを醸し出すものや、従来ウェディングの界隈でオーソドックスに使用されていた楽曲を用いず、感情が揺れ動かされやすいアーティスト楽曲(おそらく、たまたまそうした楽曲が好きなお客様がいたのだろう)を活用し、見事に感動的な映像を作り上げている。
構図も大胆なものが多く、映画さながらにフォーカスアップするものやイメージカットをふんだんに盛り込んだものなど様々だ。一部ではドローンを屋内外で活用している事例などもある。突出したクリエイターの活躍は目覚しく、同じ業界に身を置く者として感嘆するばかりだ。
話を戻すが、“強要”と先述したのにはもちろん理由がある。
繰り返しになるが、「新郎新婦のやりたいこと」を叶える場でもあるなかで、その根底を初めから無視した提案が行われているところにある。ひどいところでは「結婚式の感動を我々が作っているのだ」などと宣う企業もいるほど。
こうした話を聞いて、「なるほど、勘違いも甚だしい」と感じたのが率直な意見だ。
流行に乗った映像、おしゃれなカット、独創的な表現。いっこうに構わない。
ただそれは、流行以前からそれを実施してきた企業やクリエイター、もしくはそういうテイストを取り入れたいと奮起する個人の範疇で留めておくものであって、「こういうのが流行りだから、当式場でエンドロールをする時はこのテイストに従ってください」などと、堂々とお客様に提案をしている企業がいることが非常に腹立たしい。
独裁的な思想、雇用クリエイターに負担の波
無論、話はこれだけに留まらない。
こうした後付けで流行に乗っかった企業の採る行動には以下のようなものがある。
①高級機材、多様なレンズ、撮影アシスト機材を用いるようになった。
②通常1カメで撮影していたものを2カメ撮影をマストとするようになった。
③流行りの映像を撮影するために、一部の進行を止めたり、口出しするようになった。
④特定のBGMばかりを推奨し、『シネマエンドロール』として成り立つものを提案するようになった。
⑤流行に乗り切れていないクリエイターを卑下するようになった。
①・②に関しては、映像業界に身を置くものとして、クオリティを高めるために必要なことである。しかしながら、これらを外注、つまりは個人のクリエイターに対し強要しているのだ。
例えば、①で指した機材。これをすべて整えたと仮定すると、カメラ代で30~50万円を1台(予備でもう一台)、レンズで15~30万円を数本(3本程度)、ジンバル10万円程度、三脚・一脚・スライダー・ドローンなどは任意。これだけで見ても最低で100万円以上の機材投資を強要していることになる。
②においてはシンプルに編集者の負担が大きくなることが問題に挙がる。
少し現実的な話をするが、結婚式場におけるエンドロールの販売価格は16~25万円、高くても30万円程度というところが一般的だろう。では、実際に撮影や編集を行うクリエイターの取り分はというと、せいぜいが3万円前後というのが現状だ(中には基準が明確ではない指名制度なるものを採用し、それに応じ報酬アップを謳う企業もあるが、ここでは割愛する)。
最低でも100万円相当の出費があるにも関わらず、取り分はわずか3万円。30回以上も取り組まなければ減価償却すらできないことを半ば強制している企業が散見しているのである。
またカメラは精密機器。少しの衝撃で壊れることもあれば、雨などの水気でエラーが生じることもある。そうなれば修理・メンテナンス代が必要となり様々な出費も生まれる。これらはすべてクリエイターの自費によって賄われていることは留意したい。
③・④については最早お話にならないレベル。結婚式という厳格なタイムスケジュールが求められる場において、クリエイティビティを優先するあまりにその進行を捻じ曲げんとする輩がいる。また自分の表現を優先するあまり、他社(者)の行動などはお構いなしという風潮が見られ、周りが全く見えず配慮の欠片もないクリエイターも現れだしたほどだ。
BGMに関しては言うまでも無いだろう。なぜ新郎新婦の好きな曲を好きに選べないのか。初めから否定する姿勢はウェディングの業界においてあるまじき行動であると言える。とはいえ、正面から否定するわけではない。「あくまでもこういうテイストをオススメしています」と説明し、それでもなお違う選択を採った場合があったとしよう。ある企業では、自社のこだわりに沿った新郎新婦のエンドロールばかりを前面に押し出し、そうでないものに対しては一切触れることも表にだすことも無いという徹底ぶりだ。一種のプロパガンダを彷彿させる。
そして⑤のように、先述してきた流行を表現しきれないクリエイターを卑下し、あまつさえ「自社の提示するクオリティに足りない場合はいつまでも研修から抜けられません。なお、研修期間は無給です。交通費も出ません」といった、奴隷制度さながらなことを平気で発言する企業もいるほど。しかもそれが企業でも上役の人間が発言しているのだから救いようのない話とも言える。
クオリティの本質
では、そんな横柄な企業が出す映像のクオリティが高いのか?と問われると、「YESでありNOでもある」。
確かに、流行の映像を表現するにあたり高度な撮影・編集技術が要求されるため、レベルの高いものが出来上がってくることもあるだろう。が、しかし、その反面では映像における基本的な技術が培われていないものもある。
例えば、手振れが全く抑えられていない。表情やイメージカットを抜くことばかりに固執し画角が似通ったものばかりになっている。意味のないジンバル・広角撮影。イマジナリーラインを無視した撮影。ストーリーテリングを感じられない編集など、挙げればキリがないが、映像における基本、ウェディングにおける基本を理解していないままに応用を重視するあまり、必ずしも高クオリティの映像が仕上がっているとは言えないのが現状だ。
また、初めから編集構成ばかりを意識し、完成までの道筋が結婚式開始以前から勝手に決められていることもあり、構成に必要の無い映像を撮らない、編集しないなどという極端なものも現れ、その場、その瞬間でしか起こらなかったシーンを見逃すという本末転倒なこともしばしば見受けられている。
「クオリティを重視する」という大層な思想を掲げるあまり、視野が狭くなり、本当にその二人にとって満足のいくものが出来たのか?と問いかけたくなることもあるほどだ。
最後に
色々と思いの丈を綴ってきたが、映像表現というものは本来自由であるべきもの。多少、クオリティに差はあれど正解・不正解などはなく、各個人が最良と思えるもの作り上げていくことこそが映像の本懐ともいえる。ここに、ウェディング映像の場合は新郎新婦の思いなどを汲み取り、式場のルールや環境にも沿ったうえで、ある時は感動的に、あるときは楽しく、厳かに、ほんの少し色どりを加えることがウェディングの映像づくりの本質なのではないか。よりクオリティを高めるのであれば、当該の式場に関わる全てのスタッフを巻き込んで、すべての事柄においてクオリティを高めることが重要なのではないか。
もちろん、昨今のウェディング業界で映像展開をしている企業のクオリティが低いと感じる時もある。そうした状況を危惧し、意識を高く保つことは決して悪いことではない。ただ、その士気の高め方を間違えないでほしいというのが持論だ。
一種のブレインコントロールが横行している現状がただただ悲しく、憤りを感じ、今回このような形で筆を執った。
せめてもの願いとして、クリエイターに対しては己が潰されることがなく、凝り固まった思想に侵されずにいてほしい。これから結婚式を挙げるという新郎新婦には、主張の強い意見に流されることなく、しっかりと吟味したうえで後悔の無い思い出を残してほしいと思うばかりである。